私は母との関係に悩みながらも、物理的な距離をとることで、ようやく“介護”という関わり方ができるようになりました。
先日テレビで「親の介護特集」を見ていたときに、ある言葉が強く印象に残りました。
「親のことになると、100人いたら120人がイライラする」
きっと多くの人が、うなずきたくなるフレーズではないでしょうか。
介護は肉体的な負担だけでなく、精神的な葛藤とも向き合うものだと、改めて感じました。
だからこそ、少しでもラクに、少しでも心の余裕を保つために、スマホアプリや便利なツールの力を借りるのは悪いことではありません。
これから、実際に役立ったアプリや、気持ちが軽くなるサービスを少しずつご紹介していこうと思います。
アプリやツールに頼るのは「手抜き」ではなく「工夫」
私も50代になり、ネットやデジタルには決して詳しい方ではありません。
そうやって「使いこなせないなりに」工夫を続けることで、むしろ同世代の方々と同じ目線で向き合える情報が発信できるのではと思っています。
これからこのブログでは、実際に使って役立ったアプリや、気持ちが軽くなったサービスを少しずつ紹介していく予定です。
本当に日々情報は変化しますので、定期的に更新していきますね。
ガラケーが壊れて気づいた、今は「ガラホの時代」
私の親は80代。やはりスマホの操作が難しく、LINEなどの便利なアプリは使いこなせません。
「LINEなら通話も無料なのに…」と何度思ったことか。
困ったことがあればそのたびに電話がかかってきて、こちらの都合もお構いなし。
何度も何度も時間を取られ、イライラは募る一方。
正直、親とのやりとりに疲れ果ててしまうこともありました。
そんな時、ヘルパーさんからこう言われたんです。
「お年寄りは使えないですよ。諦めも大事です」
この言葉に、少し気持ちが軽くなりました。
そのタイミングで、母のガラケーが故障!早く用意してと電話がかかってきました。
そこで、母にはガラケーはやめてもらい、通話機能メインの「スマホ」に変えてもらいました
シンプルな携帯に変えたことで、トラブルや混乱も減り、私自身のストレスもかなり軽減されたように感じます。

今はスマホの時代です。
- ガラケー:3G回線。2026年で使えなくなる。
- ガラホ:見た目はガラケー、。電話さえできればいいのならこちらもオススメ
- スマホ:完全なタッチ操作。アプリが多機能。
今後ガラケーが使えなくなるのでお年寄りにも使いやすいスマホをおすすめします。
操作はタッチパネルですが、使いやすく設定されてます
タッチパネルの携帯に電話をしたいときは、電話のところを押せば通話できます。
もちろん、スマホなのでネット検索もできますが、電話ができさえすればいいという、お年寄りもおおいので。
やはりスマホは使えるかなと心配な方は従来の折りたたみのガラホーでも大丈夫ですが
今後ガラホー自体が需要が無いため、生産中止になることもあるらしので、最終スマホがおすすめかなとおもいます。
今、持っている携帯が故障したら どうしたらいいの
携帯電話故障したら、できれば実店舗で説明をうけたいですよね。
機種もお店で調達でき、今ある携帯を使える状態にしたいのなら、実店舗でのやり取りが一番ベストかな?と思います。
親を連れて行き、契約して使える状態しましょう
親の銀行口座で引き落とししたいのなら、親を同行していかないといけません。機種も自分が気に入ったものもその場で手に出来るので、一度親を連れて行くことになりますが。
親の身分証明書がひつようです。 写真つきのものでないとダメなので
マイナンバーカード、運転免許書 運転履歴証明書 パスポート など
なければ親の名義で契約できなくなるので、あるか確認しましょう
もしなければ、私のように契約が子供、 使用者が親って言うことも出来ますが ただ引き落としが私の口座かクレジットカードのお支払いになりますので、少したいへんかも
ちなみに立て替えたお金どうしたらいいの?これも書いてあるので参照にしてください。
親の名義に契約して 持ち帰りましょう
実際、携帯をどれにしようか親に決めてもらい、お店のひとが手続きしてくれます。
データー移行手数料 2200円
電話帳や写真などのデーターを移行してくれるサービスです
安心店頭サービス 3300円
今使っている携帯から新しい携帯に乗り換える手続きです
キャリアプランを設定しましょう
実際、携帯を使うには、キャリアでの契約をしないと使えません。
ドコモなら、サブプランのahamoなら 月々のお支払いが3000円代ですので、日々の
節約になるとおもいます。
まとめ|親のためにではなく、自分の心のために
今回はドコモの情報しかお伝え出来なかったので申し訳ないとおもいます。
親の介護に向き合う中で、頑張りすぎて自分が壊れてしまう人も少なくありません。
だからこそ、「できる範囲で」「便利なものに頼る」ことが、自分を守ることにもつながります。
今回ご紹介した内容は、実際に私が体験したことをもとにまとめたものです。
今後も良い方法があれば、またこのブログで共有していきます。
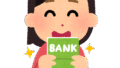

コメント