防災グッズは一通り揃えたけれど、これで本当に大丈夫?
そんな小さな不安、あなたにもあるのではないでしょうか。
実は、防災に本当に必要なのは “グッズ”だけではありません。
災害時にどう動くか――**「備えたあとの行動」**が、あなたと家族の命を守ります。
このページでは、避難ルートの確認や ハザードマップの使い方 など、今すぐできる次の備えをご紹介します。
備えたあとにするべきこと」――あなたの防災、次のステップ
防災といえば、防災グッズを揃えたり、家具の転倒防止グッズを取り付けたりしている方も多いと思います。もちろん、それらもとても大切な備えです。
でも今回は、少し視点を変えて、“知る”ことから始める防災についてお伝えしたいと思います。
まず取り組みたいのは、「ハザードマップ」で自宅周辺の災害リスクを確認することです。
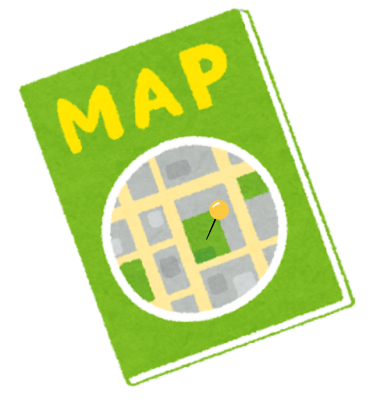
「市区村長が公開しているハザードマップで自宅周辺の災害リスクを確認しましょう」
「洪水、土砂災害、津波などの危険エリアを調べて置くことが大切です」
まずは「ハザードマップ」で、あなたの家の災害リスクを知ることから
「防災グッズを揃えたら、次は“どこで・何が起きうるか”を知ることが重要です。
そのための第一歩がハザードマップの確認です。」
「ハザードマップで事前にわかるのは、こんなポイントです」
- あなたの自宅が洪水や土砂災害、津波などの危険エリアにあるか
- 最寄りの避難所や安全な経路はどこか
- 避難にかかる時間や道のりの危険性
自分の住んでいる地域について知ることで、たとえば水害に弱いのか、土砂災害のリスクが高いのかなど、災害の種類が地域ごとに異なることがわかります。
リスクを知ることは、備えることにつながり、いざという時に適切に対処する力になります。
そしてそれが、あなたの家族や大切な命を守ることに直結するのです。
「ハザードマップを“使う”こと 命を守る第一歩」
「使う」ことで初めて命を守れる
ハザードマップを手に入れただけで安心していませんか?
実は、多くの人がハザードマップを持っているだけで「見ていない」、または**「見ても行動に移していない」**ことが分かっています。
それでは、せっかくの備えも台無しになってしまいます。
ハザードマップを“使う”ために、今すぐできること
まずはハザードマップで、自宅の正確な場所を確認しましょう。「この辺かな?」という曖昧な把握ではなく、番地や目印を頼りに、ピンポイントで位置を把握しておくことが大切です。
まずをハザードマップを開いて自分の地域を調べましょう
ハザードマップを確認したら、自宅周辺の災害リスクを具体的に書き出してみましょう。たとえば、洪水で浸水が予想される場所や、土砂災害の警戒区域、避難ルートにある川など、気になる点をメモしておくと、いざという時に役立ちます。
安全そうな場所も一緒に書き出しておくと、避難先を選ぶ際の参考になります。
最寄りの避難所までのルートを確認する
災害時に備えて、実際に避難所までのルートを歩いて確認しておきましょう。
昼間だけでなく、雨の日や夜間など、さまざまな状況も想定して歩くことが大切です。
道が暗かったり、滑りやすかったりする場所はないか、家族全員が安全に通れるかどうかもチェックポイントです。
写真を撮ったり、地図にメモをしておくと、いざという時に役立ちます。
複数の避難ルートを想定する
災害の状況によっては、いつもの避難所やルートが使えなくなることもあります。
そんな時に備えて、「Aルートが使えない場合はBへ」といった複数の避難ルートを事前に考えておくことが、命を守る備えになります。
紙の地図を防災バッグに入れておく
スマホが使えないときに備えて、紙の地図は必携。
裏に家族の連絡先や緊急メモを書いておくと、さらに安心です。

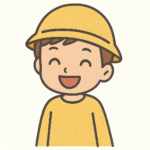
紙の地図にもいるよね災害時

事前にリュックに入れておいたらいいよ!災害時
家族と「地図を囲んで」話し合おう
ハザードマップは、家族や同居人と共有することで、はじめて意味を持ちます。
「ここが危ないんだって」「避難所はここだね」といった会話が、実際の行動力に直結します。
今から3分、自宅の災害リスクを見てみませんか?
災害時の集合場所を決めておく
災害は、家族が別々の場所にいるときに起こることも少なくありません。そんな時、自宅に集まるのが難しいことも想定して、あらかじめ**「ここで落ち合おう」と決めておくこと**が大切です。
多くの場合、近くの小学校や公民館などが避難所になりますが、家族で話し合っておくことで、いざという時も安心です。
避難するかどうか」迷わないための判断基準
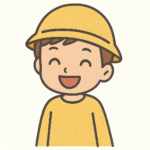
「災害って実際いつ避難したらいいのか、よく分からなくて不安なんだけど…」

「大丈夫!じゃあ今からわかりやすく避難のタイミングを説明するから、ぜひ参考にしてね!」
警戒レベル制度を知っていますか?
災害時の避難の判断には、「警戒レベル」という明確な基準があります。
これは気象庁や自治体が発表する避難行動の目安で、1〜5の5段階で示されます。
警戒レベルの基本
| 警戒レベル | すべき行動 |
|---|---|
| レベル1 | ニュースや天気をこまめに確認 |
| レベル2 | 避難所やルートの再確認 |
| レベル3 | 高齢者・乳幼児など早めに避難 |
| レベル4 | すべての人が避難開始 |
| レベル5 | 命を守る最終行動(即避難) |
ポイント
「まだ大丈夫」と思って行動が遅れるのが最も危険です。
レベル4=全員避難開始と覚えておきましょう。
🚪「避難所に行かない避難」も選択肢に:在宅避難という考え方
災害時の避難といえば「避難所」が真っ先に思い浮かぶかもしれません。
でも、すべての人にとって避難所がベストとは限らないんです。
たとえばこんな場合、**「在宅避難」**のほうが安全で快適に過ごせる可能性があります:
- 高層階に住んでいて浸水リスクが低い
- ペットがいて避難所に入りにくい
- 高齢の家族や持病のある人がいて移動が難しい
- 感染症や集団生活の不安がある
とはいえ、自宅にとどまるには備えと判断力が必要です。
「水はどれくらい必要?」「トイレは?」「停電対策はどうする?」――
こうした具体的な在宅避難の備えについてはこちらで書いてます。
自宅でいられるなら それに越した事はありませんよね。そのためには事前準備が大切です
ハザードマップを確認したあとの自宅での台風などの場合どうしたらいいか、こちらの記事でも書いてます
ぜひ覗きにきてください 台風に備える!揃えた家庭の防災
まとめ:「グッズ」だけじゃ足りない、“行動”が命を守る
防災グッズを揃えることは素晴らしい第一歩ですが、
本当に大切なのは「その先にどう動くか」です。
ハザードマップで自宅のリスクを知り、避難ルートを確認し、家族と話し合う。
こうした“ちょっとした行動”の積み重ねが、あなたと大切な人の命を守る力になります。
✅ 今すぐできること:
- 自宅周辺のハザードマップを確認
- 避難所まで実際に歩いてみる
- 紙の地図と家族連絡先を防災バッグに入れる
- 待ち合わせ場所をあらがじめ決めておく

地震のように予測が難しい災害に備えて、家族で待ち合わせ場所を決めておきましょう。
台風など事前に準備できる災害には、家庭でできる対策を早めに整えておくことも大切です。

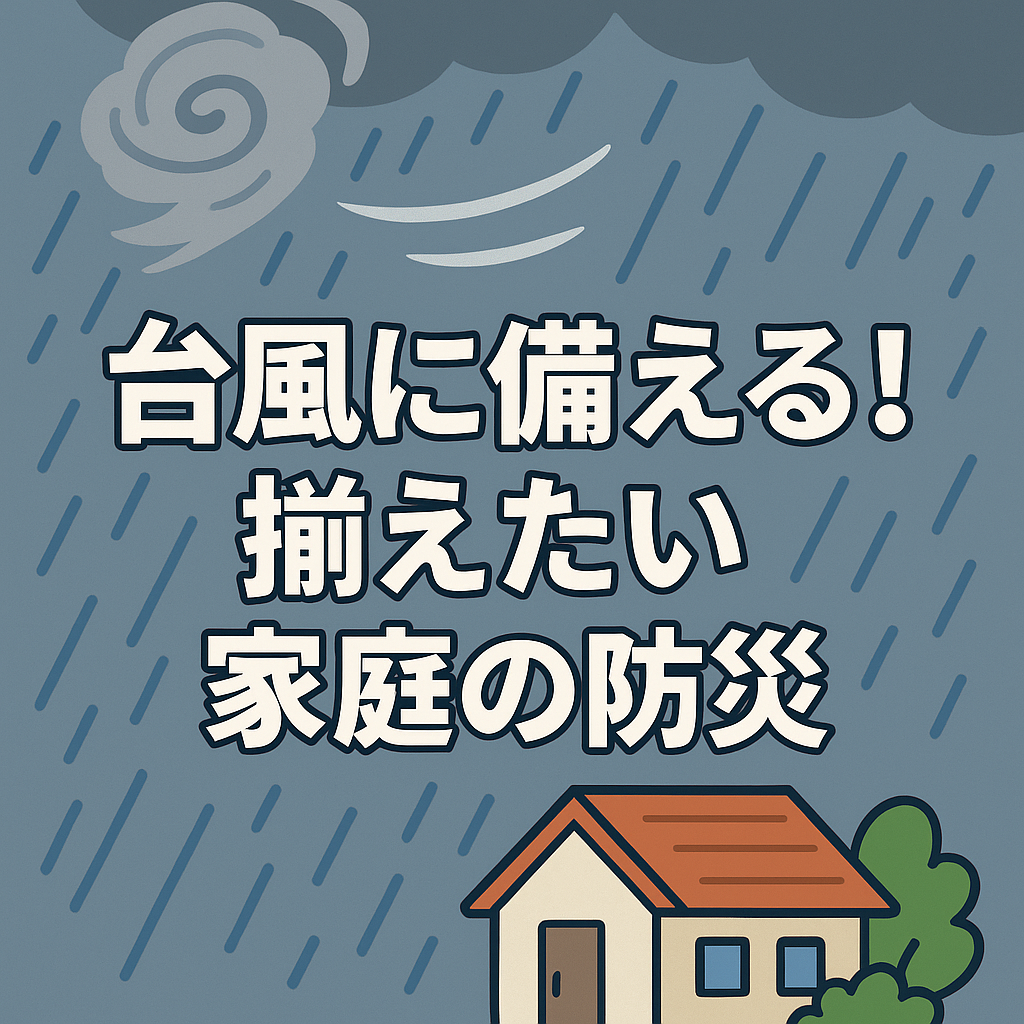

コメント